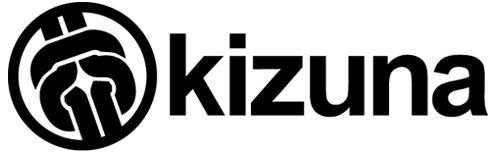昔は、清涼飲料を瓶で飲んでいた。使い捨てプラスチックボトルが普及する前、空瓶を木箱に詰めて、店に返し、また、飲み物を買ったものだ。おじいちゃんはいつも緑色の小瓶の「ガラナ」を買って冷蔵庫に入れ、孫たちが来るのを待っていた。栓抜きで瓶の蓋を開けたときのガスの音を聞くと、私は、今でも、昔のキッチンを思い出す。
そこには、まだ子供だった私と頼りがいのあるおじいちゃんがいる。ポルトガル語がよく話せなかったおじいちゃんだったけれども、私に愛情をたっぷり注いでくれているのが分かった。
おじいちゃんは独り住まいだった。部屋は薄暗く、ちょっと古くて、片付けているのか、いないのか、おばあちゃんが何年も前に亡くなったのにその頃と変わっていなかった。私はおばあちゃんを知らないけれど、おばあちゃんのいた時代にタイムスリップしたようだった。
父とおじいちゃんの話によると、おばあちゃんは、私が生まれて何か月かして亡くなった。亡くなる直前に、私を抱いてあやしたと、おばあちゃんはうわごとで言ったそうだ。これはおじいちゃんの最も悲しい記憶として残り、おじいちゃんは、私がおばあちゃんの生まれ変わりだと信じ込んでしまった。そのため、私はおじいちゃんのお気に入りの孫娘になったのだ。
おじいちゃんがどの宗教を信仰していたかは分からないが、私は長年こう考えてきた。「おばあちゃんが亡くなった時には、私はもう生まれていたのだから、生まれ変わりなんてことある?私はもう自分の魂を持っていたはずなのに。私の人格に問題があるのは、そのせいかもしれない。私の元々の魂は、死んでしまったおばあちゃんの魂に追い出されたのか、それとも、おばあちゃんの魂が乗り移ったのか?」
おじいちゃんの私への愛情は、自分自身で勝ち取った愛情ではなく、おじいちゃんのおばあちゃんへの愛情から引き継がれたものだった。おじいちゃんが50年も妻を愛し、おばあちゃんが死んでからも、思い続けることができるのはすばらしいことだと、私は少しずつ思うようになっていた。
父は、自分の両親が、一度も、人前で、愛情表現をしなかったことを不思議に思っていた。実際、昔の日本人の夫婦はそんなものだった。
家中におばあちゃんの写真があり、おじいちゃんはそれを愛おしそうに眺めていた。もう疲れたから早くおばあちゃんのところへ行きたいと言ったとき、私は驚いた!(え、おじいちゃんがおばあちゃんに会うためには私も死ななきゃ!それとも、おばあちゃんの魂が私から抜け出れば、私の元々の魂が再生するのかしら?)おじいちゃんが死にたいという気持ちが理解できなかった。私の身近な人は誰もそんなことを願っていなかった。私はショックだった。
すると、おじいちゃんはテーブルの上の新聞の死亡欄のページを開いて言った「毎日、新聞で友人が死んだか調べているんだ。葬式へ行くためになぁ。ジイチャンの友人は、亡くなっている人の方が多い。バアチャンも死んでしまったし、ジイチャンは独りになって疲れてしまった!」
おじいちゃんは、死は怖くないと、教えてくれた。
季節ごとの行事には、おじいちゃんはいつもお小遣いをくれた。封筒に私たちの名前を漢字で縦に書き、中に入っているお金でノートを買うようにと、言った。けれども、姉と私は、ノート以外の別のものを買おうと楽しみにしていた。
おじいちゃんは教育をとても大事に考えていた。若いころ、学問を身につけずにブラジルに来て、パラー州でブラックペッパーの栽培に取り組んだ。子供たちの教育のためは犠牲を厭わなかった。息子たちは、大学を出て、建築家、エコノミストとエンジニアになった。一人娘には勉強ではなく、結婚を勧めた。しかし、孫娘には教育を受けさせることを望んだ。時代が変わり、おじいちゃんの考え方も変わっていった。お小遣いの袋には、お金と一緒に「第一は健康、第二は勉強、そして三番目は友達」と、いうメモが入っていた。学問は、誰も奪うことができない、とおじいちゃんは言っていた。
おじいちゃんは、一度日本へ戻った。人生の一大イベントだった。日本移民の代表団の一員として、日本の天皇から金のネクタイピンを賜った。そのピンはおじいちゃんのたった一つの宝物だった。おじいちゃんが亡くなった時、棺に入れて一緒に火葬した。旭日旗の太陽とそこから広がる光線が浮き彫りになっている旗のデザインだった。おじいちゃんは、他には何も持っていなかった。
仏教徒として地味な生活を送っていた。と、言っても、おじいちゃんの宗教は仏教だったか、はっきりとは分からない。多くのブラジル人のように、色々な信仰に従っていたようだった。
家で靴を脱ぐと、おじいちゃんの靴下に穴が開いていることがよくあったので、だから私はいつも靴下をプレゼントしていた。しかし、おじいちゃんが亡くなり、家族で遺品を片付けていると、私がプレゼントした靴下がたくさん見つかった。タグ付きで、パッケージの中に入ったままだった。一度も履いていない靴下を見て、私は貰った物はすぐに使おうと思った。おじいちゃんのように大事に仕舞っておくだけでは、何の意味もないし、温かい靴下の気持ち良さも味わえないから。でも、私はもう一つおじいちゃんについてわかったことがあった。おじいちゃんは、靴下に穴が開いているかどうかなんて、気にしていなかったってことだ。
おじいちゃんの思いに応えられなかったと言う罪悪感と反省が交じり合う。今でも、おじいちゃんへの思い出は優しさで溢れている。もっと、おじいちゃんの側に居てあげるべきだった。子供時代は罪悪感など持ち合わせていない。罪悪感は、成長するにつれ、めばえてくる。
おじいちゃんが亡くなった日に、罪悪感が込み上げた。
入院中のおじいちゃんを見舞いに行くと、おじいちゃんはいつも私の手を握って、家に連れて帰ってくれと、懇願した。私は戸惑った。父や伯父たちの決断次第なので、何も言えず、手を離し、部屋を出て行かざるを得なくて、外で泣いた。おじいちゃんも私も何もできなかった。おじいちゃんを家に連れて帰ろうとは、父に言えなかった。病院で治療を受けている方が、おじいちゃんの回復に良いと思っていたから。
おじいちゃんが亡くなり、私はもし誰かに同じようなことをまた頼まれたら、絶対にその人を家に連れて帰ってあげようと決心した。人は自分の死期が分かる。おじいちゃんは、自分の最期は病院ではなく自宅で迎えたかったのだ。
おじいちゃんは、私が初めて見た死んだ人だった。鼻に綿が詰められ、靴はむくんだ足に履かせるために側面がカットされていた。まるで眠っているようだった。私は頬を軽く口づけをした。姉と一緒に泣いた。激しく泣いた。私たち二人は、とても悲しんだ。悲しんでいる姉を見て、私は、私がおじいちゃんのお気に入りの孫だったと絶対に言わないようにしようと誓った。今はどうでも良いことだが-、おじいちゃんは人生で初めて、私を大切に思い、愛情を注いでくれた人だった。
私はおじいちゃんの死に涙したが、それ以上に、自分自身にも涙した。私を可愛がってくれたおじいちゃんは、最後に苦しんで、この世を去ってしまった。私はおじいちゃんを病院から家へ連れて帰ってあげられなかった。おじいちゃんはずっと、亡くなったおばあちゃんに会いたがっていた。私への愛情は、もう、無くなっていたのだ。私はもう泣くのは止めた。そして、おばあちゃんの魂が私から抜け出し、ようやく、私は本来の自分に戻れた。
おじいちゃんが亡くなってから今年で24年になる。11月19日生まれのさそり座のおじいちゃん。たくさんのことを教えてくれた。おじいちゃんが日本人だったからか、よく分からないが、おじいちゃんの愛情に包まれて過ごした時を思い出すと、私も日本にルーツがあるということが、とても誇らしい。80年代のブラジルで育った私は、マスメディアが「日本人」を軽蔑し、偏見を持って、ステレオタイプ的に、放映するのを見て、とても悔しかった。だって、おじいちゃんも私もそのような扱われ方は嫌だったから。
そして今、父はオジイになった。私のおじいちゃんは、今、父の中にいる。息子たちのオジイは孫を愛称で呼び、お小遣いはアイスクリームとおもちゃを買うためだと言う。まんじゅうを買って、うちに泊まり、孫と相撲を取って、日本語も教えてくれる。そして、私のおじいちゃんのように、孫と楽しい思い出を作り、日本の良さを伝えていく。
父は孫息子が自分の父親の生まれ変わりだと信じ込んでいる。つまり、私の息子は私のおじいちゃんの生まれ変わりということだ。全てが同じ。人生は輪のように廻り、日本は我が心に。
* * * * *
このエッセイは、シリーズ「ニッケイの世代:家族と コミュニティのつながり」の編集委員によるポルトガル語のお気に入り作品に選ばれました。こちらが編集委員のコメントです。
クラウディオ・ハジメ・クリタさんからのコメント
このプロジェクトの編集委員の一員になれて、とても光栄です。今年のテーマ「ニッケイの世代:家族とコミュニティのつながり」に応募があった多くのエッセイは素晴らしく、執筆者の方々は、それぞれ、自分の体験をしっかりと語っていて、その中でも、アナ・シタラさんの「2人のおじいちゃん」は感動的でした。
この作品を読んでいると、読者は作品の中へ自然に引き込まれ、自分の祖父母のことを思い出し、その生きた時代が思い浮かびます。そして、どの家庭にもある激しくぶっつかり合う愛情、感情、後悔という様々な気持ちが描かれていることにより、読者はその内容に親しみを感じることができます。
また、著者の祖父は教育を大切に思っていたと書かれています。これは一世・二世の世代の考え方でした。子供たちの将来のために、親たちは一生懸命に働きました。初代の努力のお陰で、今の若い世代の多くは経済的、社会的位置が高く、様々な分野で活躍しています。
私は父方、母方の両方の祖父母に感謝しています。アナ・シタラさんにも感謝しています。なぜなら、このエッセイを通して、私の祖父マルオさんやアキカズさんのことを思い出したからです。二方にお礼を申し上げます。
ディスカバー・ニッケイのプロジェクトに参加させていただき、ありがとうございます。世界中の日系コミュニティの文化を一つにして、それを広めていくサイトの役割は見事で大切だと思います。
© 2021 Ana Shitara