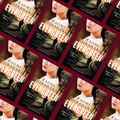バスの前方の窓からは、北カリフォルニアの暑く乾燥した夏の、何エーカーもの天日干しの草地が見えました。道路の両側には、私たちの家族の多くが何年もの間、武装した警備員と監視塔に囲まれ、プライバシーがほとんどない、タール紙でできた密集したバラックで暮らしていたのと同じ、有刺鉄線のフェンスが立っていました。
「皆さんの中で、第二次世界大戦以前、あるいは戦時中にここにいたことがある人は何人いますか?」とガイドが尋ねた。70代、80代、あるいはそれ以上の年齢の日系アメリカ人が数人手を挙げた。ガイドが次に言った、ほとんど何気ない一言に、私たちの多くは唖然とした。「おかえりなさい。」
ガイドは、私たちの長老たちを戦時中に収容されていた場所に迎え入れたのだろうか?私たちの間で落胆したざわめきが起こった。
ガイド(この地域巡礼のためにトゥーリー湖委員会と提携している公園管理人)が言いたかったのは、「あなたが戻ってきてくれて光栄です」ということだと思います。これは、日系アメリカ人強制収容所の生存者の直系の子孫として私が直面する奇妙な修辞的状況の1つにすぎません。
社会として、私たちはまだ日系アメリカ人の戦時強制収容の被害を認識するための適切な語彙を発達させているところです。適切な説明やラベルがないため、私が 2014 年に始めたようなコミュニティ巡礼は誤解され、判読できず、または見えなくなります。そして実際、間違った言葉は、生存者や子孫が日系アメリカ人の強制収容所跡地を訪れ、私たちの歴史を尊重し、癒すことを妨げる可能性があります。
私の父(私が10歳のときに亡くなりました)とその家族は、第二次世界大戦中、カリフォルニア州トゥーリーレイクに4年近く収監された約3万人の人々の中にいました。戦時中、米国政府は合計で12万5千人以上の「日系人」を収監しましたが、そのほとんどは西海岸出身者でした。彼らのほぼ3分の2は、正当な手続きなしに拘留された米国市民でした。
非営利団体「デンショウ」は、刑務所や市民隔離センターから強制収容所、軍が所有・運営する連邦刑務所まで、全米の日系アメリカ人収容施設約100カ所の地図を作成した。
現在、これらの場所のほとんどは、目に見える歴史的標識もなく、風景の中に消え去っています。残っている場所も、地域の巡礼の道が閉ざされる恐れがあります。最もよく知られている闘争の 1 つは、アイダホ州のミニドカ強制収容所跡地で起こっています。そこでは、計画中のラバリッジ風力発電所が、かつて 13,000 人以上の日系アメリカ人を収容していた同じ砂漠地帯に、高さ 720 フィートの風力タービンを何百基も設置する恐れがあります。
国立歴史保存トラストは、ミニドカを2022年に最も危機に瀕している11の歴史的場所の1つに選びました。キャンプの建物のほとんどは消滅しましたが、現在、この場所は毎日訪問者に公開されており、夏の週末にはガイド付きツアーが開催されています。
風力発電所はミニドカの公教育の可能性を台無しにし、現在訪問者が目にしている遠く離れた荒涼とした眺望を永久に破壊するだろう。さらに悪いことに、土地管理局の2023年環境影響評価書草案では、当局はミニドカを「レクリエーション」の場として挙げている。
これに対し、日系アメリカ人の生存者、子孫、非営利団体「ミニドカの友」の支援者たちは、この用語に反対する強力なキャンペーンを展開した。「私は観光客ではありません」と、抗議活動家ポール・トミタが掲げたポスターには書かれていた。そこには、ミニドカで幼少期を過ごした彼の写真が載っていた。「私は生存者です」
ミニドカで起きていることは、国中で起きている。6年前の2017年、私は他の日系アメリカ人活動家たちとともに、トゥーレ湖飛行場の周囲に長さ3マイル、高さ8フィートの有刺鉄線フェンスを張り巡らす計画を阻止するための地域抗議活動を組織した。トゥーレ湖飛行場は強制収容所の敷地内にあり、現在はオクラホマ州モドック族が所有している。このフェンスが建設されれば、事実上、一般人の立ち入りが禁止されることになる。
この歴史的な場所にまたもや鉄条網フェンスが設置されたという屈辱は、遠くから抗議を呼び、個人や団体から約5万通の手紙と署名が集まった。「私たちはずっとフェンスと共に生きてきた」と、私の亡き叔父でトゥーリー湖の生存者であり詩人の柏木博氏は、2017年にその建設に抗議する詩の中で書いている。彼はフェンスの力をよく知っていた。その力は彼や他の生存者たちの人生にずっと付きまとってきた。
トゥーレ湖では、飛行場のフェンスはただ一つの問題に過ぎません。この場所とその歴史を管理する人々は、10年以上もの間、さまざまな団体間の争いに悩まされてきました。これらの団体には、連邦航空局、国立公園局、トゥーレ湖市、モドック郡、モドック族、地元の農家や牧場主、そして日系アメリカ人の生存者と子孫の2年に一度の地域巡礼を組織する、ボランティアのみで構成されているトゥーレ湖委員会(私も理事の一人です)が含まれます。
これらの組織はそれぞれ、収容所が元々あった 1,100 エーカー以上の敷地全体のうち、一部に対する保護、アクセス、利害関係、管理の程度が異なっており、そのうち 37 エーカーのみが国定記念物として保護されています。現在、約 359 エーカーの公共飛行場が、74 棟の兵舎があった元の強制収容所の敷地の中央にあります。
これらの建物は戦後撤去されましたが(多くは土地の寄付を獲得した入植者のために近くで再利用されました)、ここは日系アメリカ人の生存者と子孫が訪れたい、また訪れる必要がある主要な場所の 1 つです。
言葉でこのもつれを解くことはできないが、その重要性を明らかにすることはできる。トゥーレ湖は、第二次世界大戦中の日系アメリカ人強制収容所の中でおそらく最も悪名高い。収容された日系アメリカ人の忠誠心を判断するために政府が不適切な表現の質問票を実施した1944年、収容者数は1万8000人でピークに達した。無条件の忠誠を誓うことを拒否した者はトゥーレ湖に移送され、そこは「トラブルメーカー」の収容所、「不忠者」の隔離センターとして知られるようになった。
元トゥーリアンの多くは、戦後何十年もそこに収容されていたことを認めたくなかった。日系アメリカ人コミュニティー内でさえ、アンケートに否定的な回答をしたノーノー(私の叔父ヒロシを含む)のように、何らかの形で抵抗した者は、疎外され、追放された。この歴史は、今も語り継がれ、評価され続けている。
私たちがこれらの場所をどう認識するか、また、その場所を訪れる人々にどう名前をつけるかが重要です。戦争中、政府は婉曲表現を使って、無期限の拘留を「戦争中」と言い換え、臨時の拘留所を「集合センター」と言い換えました。
ほんの10年前、私は「強制収容」という最も一般的に使われる言葉が、大量投獄や強制収容所の現実を覆い隠していることを理解した。(厳密に言えば、それは第一世代の一世にも当てはまる。)ここ25年ほどで、コミュニティ自体が、強制収容に「トラウマ」という言葉を、そして年々減少している収容者に「生存者」という言葉を当てはめるようになった。
マンザナー強制収容所の生存者であり研究者でもあるアイコ・ヘルツィグ=ヨシナガ氏はかつてこう書いています。「言葉は嘘をつくこともできるし、明らかにすることもできる。」これをさらに深めてみましょう。言葉はこの歴史について嘘をついてきたので、私たちがそれをどのように記憶しているかを明らかにするべきです。
トゥーリー湖の巡礼バスの中で、私は、囚人たちが作った埃っぽい監獄の中から、武装した警備員がかつて使っていた木造の塔の基部から、あるいは、その道を渡る者を傷つけるために作られた有刺鉄線のフェンスの横から見ると、自由は違って見えることを学んだ。
後になって、その旅で私たちが何をしていたかを表す言葉が思い浮かびました。私たちは宗教的な理由でトゥーレ湖にいたわけではありません。また、祝福を受けるため、あるいは奇跡が起こった場所を見るためといった、伝統的な巡礼の意味でそこにいたわけでもありません。しかし、私たちの旅の目的は超越的で精神的なものだったと言えます。それほどまでに、私は今、そこで過ごした時間を表すのに、ためらいながら、宗教的な意味合いを持つ別の言葉、つまり「交わり」を使うでしょう。
*このエッセイはもともと、メロン財団の支援を受けたソカロ公共広場の調査「社会はいかにして自らの罪を記憶すべきか?」のために書かれ、 2024年2月11日に羅府新報に再掲載されました。
© 2023 Tamiko Nimura